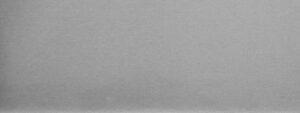旋回(捻り)動作──伝統・現代・痛みをつなぐ身体感覚の進化

私たちは「捻る」という動きに、どんなイメージを持っているだろうか。
スポーツや武道、ダンス、日常のちょっとした所作――
そのすべてに、実は“旋回”という動きは深く関わっている。
一方で、腰痛をはじめとした身体の不調と、「捻る動作」との関係に悩む人も少なくない。
このテーマを、伝統と現代の両面から考えてみたい。
◆ 捻りを抑えた伝統的な日本の動き
日本の古来の生活様式や身体文化には、「捻りを最小限にする」特徴がある。
たとえば農作業や武道、伝統芸能、正座やすり足、ナンバ歩き――
体幹をひねらず、全身の“面”で動く。軸を通して力を流す。
こうした所作は、草履や和装、畳の上での生活と不可分に発達してきたものだ。
結果として、腰や膝、首などに局所的な負担が集中しにくい、調和的な身体運用が成立していた。
◆ 変化した現代の動き──「旋回」は進化か、リスクか
時代が変わり、私たちは洋服・靴・椅子・車社会へと生活様式を大きく転換した。
西欧的な動作――大きく腕を振る、体幹をダイナミックに捻る、パワフルなランニングやスポーツの動き――
こうした「旋回」が日常動作のなかにも深く入り込んでいる。
沖縄空手をはじめとする武道や多くのスポーツでも、
旋回を巧みに取り入れることで生まれるダイナミズム、パワー、しなやかさが、技法の進化を促している。
現代の身体性には、「捻りを否定するのではなく、どう合理的に活用し、昇華できるか?」という発想が不可欠だ。
◆ 旋回動作と腰痛の関係性──“部分の捻り”のリスク
ただし、旋回が持つ“影の部分”にも目を向けなければならない。
- 本来、腰椎(腰)は回旋可動域がきわめて小さい。
- 腰だけをひねるクセがつくと、筋肉や椎間板、靭帯への負担が極端に増え、腰痛や怪我の原因となる。
現代日本人に腰痛が多い背景には、
「伝統的な全身運動→局所的な回旋動作へのシフト」がある、と考えることもできる。
◆ 武心脱力™の視点──旋回と軸、調和の技法へ
私は旋回(捻り)そのものを否定しません。
むしろ、現代社会の多様な動きのなかで、旋回は進化と創造のカギとなる動作だと考えます。
大切なのは、
- 「どこで、どう伝えるか」
- 「部分の捻り」ではなく、「軸を保った全身の連動」
- 「力を抜き、丹田や股関節・胸椎など、可動性の高い部位で回旋を受け流す」こと
沖縄空手のように旋回を高度に昇華した武道がヒントになる。
現代的な合理性と伝統的な知恵、その両方を生かしながら、身体の痛みや不調と向き合っていく姿勢が大切だと感じています。
◆ まとめ──伝統と現代を結ぶ、新しい身体感覚へ
「旋回」は、私たちの身体をより自由に、よりパワフルに使うための道具だ。
ただし、その扱い方を間違えば、腰痛や不調の原因にもなる。
伝統的な“軸”の感覚と、現代的な“旋回”の合理性。
両者を対立させるのではなく、調和させることが本当の進化につながると、私は考えます。
痛みや違和感を無視せず、身体の声に耳を傾けながら、
あなた自身の“心地よい旋回”を探してみてください。
武心脱力™は、伝統の知恵と現代の技法をつなぐ、
「自由な身体感覚」の獲得をめざします。